KAMADA ANJU
Tamabi Online Portfolio

3Dアニメーションの「違和感」について
近年、アニメーション表現は手描きから、ゲームなどではLive2Dへ、
テレビアニメでは3Dへと多様化している。これらはすべて「動く絵」を扱う
表現だが、視覚的な印象や受け手の感じ方には大きな違いがある。
私は手描きアニメーションもLive2Dアニメーションも3Dアニメーションも、
それぞれに魅力と強みがあると思う。しかし、手描きで描かれていたアニメが
急に3DCGになると、どこか違和感を覚え、ストーリーに集中できなくなることがある。この感覚を持つのは私だけではないだろう。
どんなに映像が美しくても、物語が伝わらなければアニメーションの意味が
無くなってしまう。
そこで私は、3Dアニメーションに生じる違和感の理由と、その解決方法を
考察することにした。
TVアニメで見慣れている状況から手描き→Live2D→3Dの順で違和感があると
考える。
まず、手描きアニメーションとLive2Dアニメーション・3Dアニメーションの
違いを分析していく。
《それぞれの視覚的な印象の違い》
手描きアニメーションは、1枚1枚の絵を描いて連続的に見せることで動きを
作る方法である。
線の震えや描き手の癖がそのまま動きに反映される。動きは現実より単純化され、強弱のある線や間の取り方で感情を表現する。たとえばキャラクターが
振り向く一瞬に、わずかに誇張されたタイミングを入れることで、現実には
存在しない“気配”や“心の動き”を描き出すことができる。
また、ワンカットしか出ないような細かい小物も凝って描くことが出来たり、
キャラクターの寄りと引きで密度を変えて見栄えをコントロールすることも
出来る。 形状やボリューム感を自在にコントロールすることで
リアリティ(もっともらしさ)が強調され、“心地よい嘘”を作り出すのだ。 手描きアニメーションの魅力は、この「省略と誇張の美学」にある。視聴者は
実際の運動を見ているというよりも、「動きの印象」を見ているのだ。
一方でLive2Dアニメーションは、手描きのイラストを分割しパーツごとに
変形させて立体的に見せる方法である。
もともと2Dの絵であるため、手描きの質感や塗りの雰囲気をそのまま
保ちながら立体感を加えなめらかに動かすことができる。 元のイラストを
基準とした微妙な首の傾きやまばたきなど、限られた範囲の動きでは非常に
自然に見える。髪や布等の柔らかく変形するものの動きは1番自然で
動かしやすい。 しかし画角を滑らかに移動したり複雑な身体の回転になると、構造的な制約から不自然さが生じやすい。
Live2Dは「平面を立体的に錯覚させる技術」であり、実際に立体を
操作しているわけではない。そのため、観る側は“2Dの絵が動いている”と
いう意識を保ったまま、アニメーションを受け入れやすい。
動きと静止画の中間、手描きと3Dの中間に位置する表現といえるだろう。
そして3Dアニメーションは、立体的にモデリングされたキャラクターや背景をコンピュータ上で動かす方法である。
カメラの視点を自在に動かせるため、現実の映画のような演出が可能であったり逆に考えられないような不可能な演出が可能である。
全員違う見た目のスクランブル交差点のような状況は苦手だが、軍隊のように
同じ見た目で同じ動きをするキャラクターを作りやすく、硬くあまり変形しないものの動きを作りやすい。
また、正確な動きの再現が得意で、人間の普段の動きをリアルに再現できたり
重力や慣性といった物理的な要素を計算的に扱える点は、他の手法にはない強みである。
3Dアニメーションの魅力はこの「現実の再現」にある。
手描きアニメーションの短所を3Dアニメーションが、3Dアニメーションの欠点を手描きアニメーションが補えると言えるだろう。
ではなぜ3Dアニメーションが手描きアニメーションに溶け込めないのか。
手書きアニメーションの中に3Dアニメーションが入った時の違和感について
考察していく。
《3Dアニメーションの違和感》
①物理現象が上手くいかない
髪や布のように柔らかく変形するものに塊感が出てしまう。

髪がなびいたとしても束になって動いていたり服のシワの変化量が少なくなる。 また、関節事に塊感が出ることが多く、特に肩周りに布があるとごつくなり、
腕と胴体がバラバラに見えてしまう。
手描きの背景と矛盾が生まれる

影が固定されたり、重さがおかしくなったりする。
影は一方向からの強い光は作ることが出来るが反射光や、環境の変化による
光の変化に対応できていない。重さは本来の人間の動きを参考にしているため、等身の合わないキャラクター等では体重のかけ方がおかしくなったりする。
②情報量が一定になってしまう
寄りと引きの情報処理が上手くいかない

手書きアニメーションでは寄りと引きやキャラクターの心情によって
書き込みの情報量を変えてキャラクターの印象を捜査する。
が、3Dアニメーションではモデルを変形させることが難しい。
最初からモデルの書き込みを抑えてしまうと寄りの時に弱くなってしまい、
最初からモデルを書き込んでいると目が散ってしまう。
ポーズによって等身の変更ができない

手書きアニメーションではキャラクターの印象を強める時にわざと等身を変え、複雑なポーズをとる時や物語が進展する時に正しい等身に戻したり変形させる
ことがある。
具体例を挙げると、マスコット的なキャラクターに腕を組ませようとしたら
腕が伸びたりすることがある。
が、3Dではそれが出来ない。作画崩壊はしない代わりに魅力が描ききれなく
なる。
直線的でノイズが発生しない

3Dの状態では不自然でなくても、トレースをしたり縁の線を強めると、直線的で固くマネキンのような印象になってしまう。影や色の情報が減ると直線的になってしまい、コントラポストを誇張した曲線の多い手書きの方が違和感が無くなる。
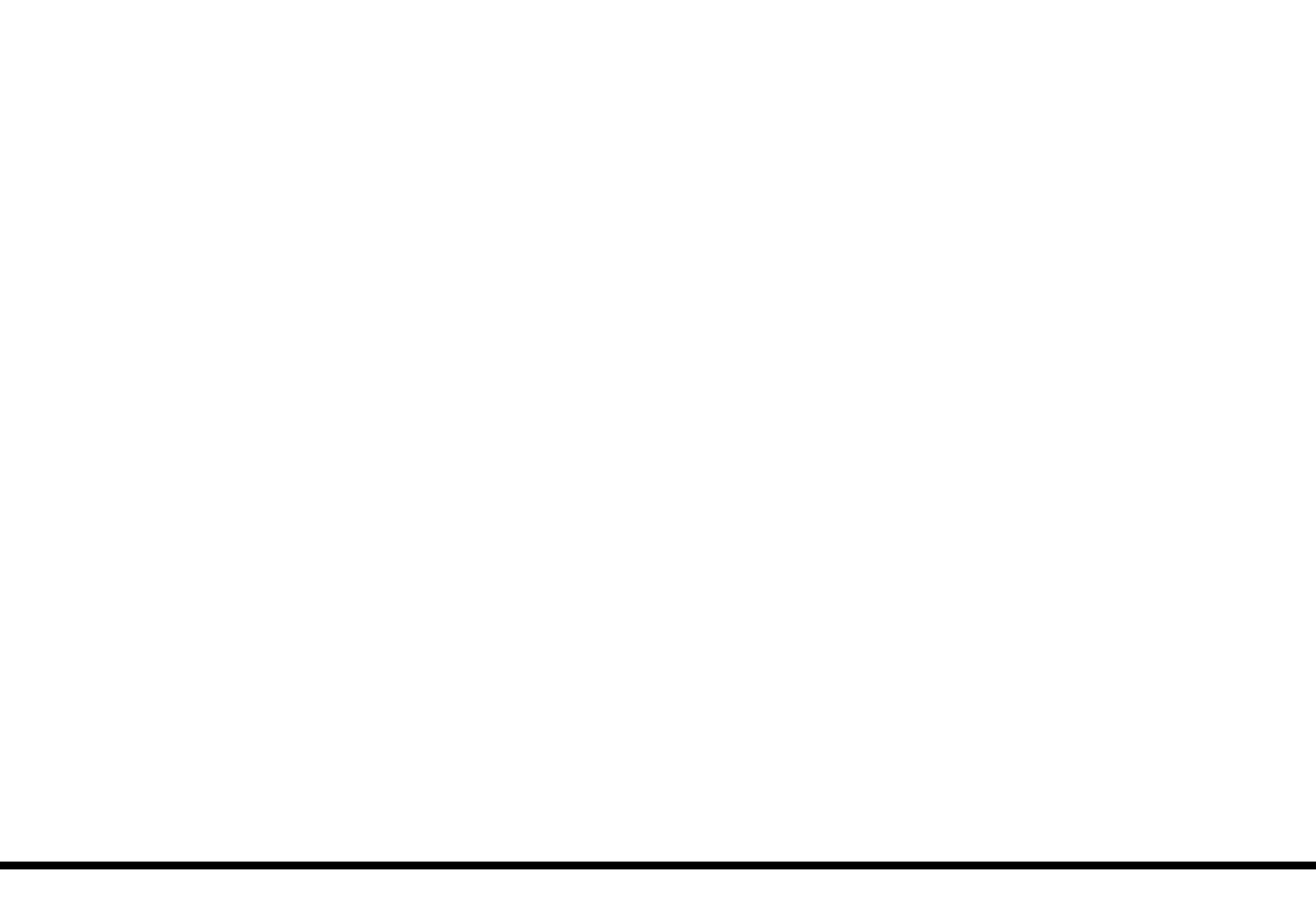

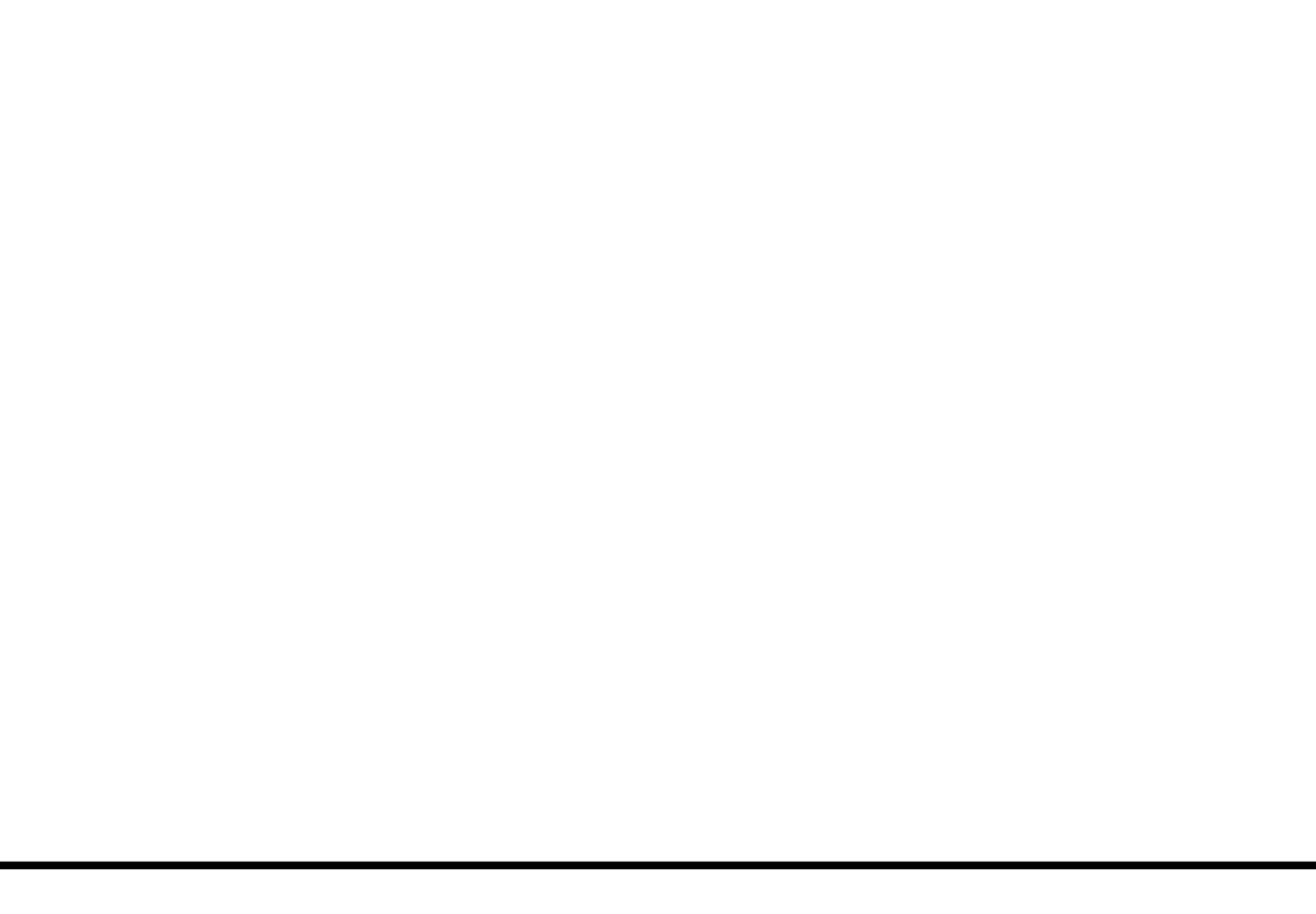

また、ボールなどが跳ねる動きも綺麗な円(楕円)が動くだけでは躍動感が出ず、手書きで出る筆のブレがノイズとなって躍動感が出る。
③フレーム数が違う
手書きアニメーションは1秒につき8枚のフレーム
(フルアニメーションでは1秒につき24枚のフレーム)で構成されているが、
3Dアニメーションは基本24fpsが多い。 周りの情報に比べて滑らかに
動きすぎているためキャラクターが浮いているような違和感があるのでは
ないか。
②の「情報量が一定になってしまう」が多いように感じたので②を中心にどのようにすればこの違和感が解消されるのか考えてみる。
《違和感の解決法》
❶シルエットが大きく変わる変わるような少し大げさな動きをつける
リアルな人間の動きでは情報量の変化が少なくなってしまい、直線的に感じたり違和感がある出てしまう。アメコミやカートゥーンのような少し大げさではやい動きをつけることで、画面が一気に動くので背景とのフレームレートの違いが気にならなくなったり情報量が増えのではないか。
❷輪郭を細かく動かす

キャラクターが移動している時や喋っている時に輪郭の縦横比を細く変えたり、髪のボリュームをわざと変える。これによって手書きのような変化を与えることが出来るのではないか。 特に怒ったり笑ったり大きな感情の変化が起こるシーンで使うとよりキャラクターの感情が映えると思う。
❸ねじれた部分のシルエットを変える

手首を捻ってもあまり肘は回転しないのに必要以上に回転してしまったり、体を正面に向けた状態で首から上だけ横を向いても首の太さは変わらないはずなのに細くなってしまったり、3Dでは結合部分の比重の関係で関節を動かしたりねじった時にその部位が細くなってしまうことがある。そのシルエットを直してあげることで部位ごとでバラバラに見えることはなくなるのではないか。
❹カメラを移動する時に背景の動きをあえて変える

カメラを素直に動かしてしまうとキャラクターが必要以上に立体に見えすぎて2Dの背景に溶け込まない。 キャラクターをカメラが回転する向きと同じ向きに動かし、現実で背景通りに撮った時よりもキャラクターの見える範囲を狭めることでなめらかさを合わすことが出来るのではないか。
❺フレームレートを下げる
フレームレートを8fpsにして手書きアニメーションと滑らかさを合わせれば浮いているような違和感が減るのではないか。
3Dアニメーションの「違和感」は、単なる欠点ではなく、
表現の可能性を広げるためのヒントだと私は感じている。動きを正確に
再現できる3Dだからこそ、正確さと自然さ・見せたい絵のバランスを見つけ、それを実現出来るプログラムを考えていくことがこれからの課題だと思う。
今後は貴学で、
ブレイクダンスの様な多くの筋肉を使い色んな角度からキャラクターが見える動きはどうすれば自然に手書きアニメーションに溶け込ますことができるのか。や、
動物の生きた動きは3Dアニメーションの中ではあえて消した方がいいのか、それとも誇張した方がいいのか。どう表現できるのか。
を研究していき、3Dアニメーションを通してストーリーや感情がより自然に伝わる映像表現を自分の手で進化させていきたい。
